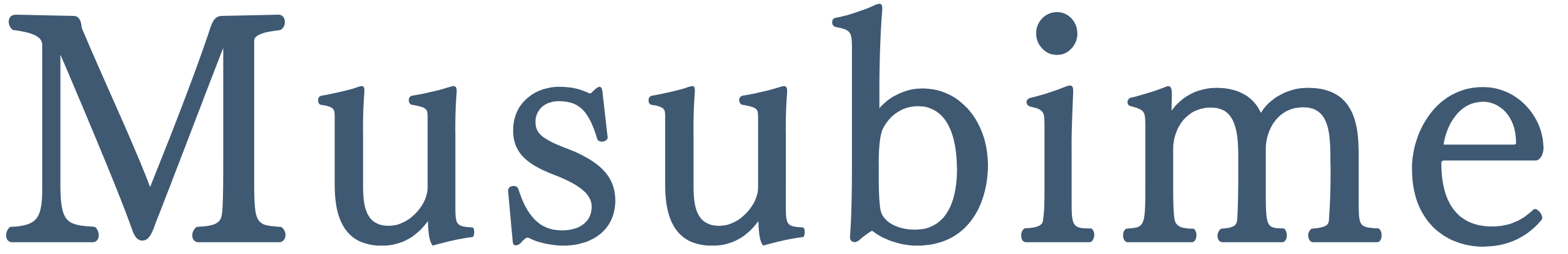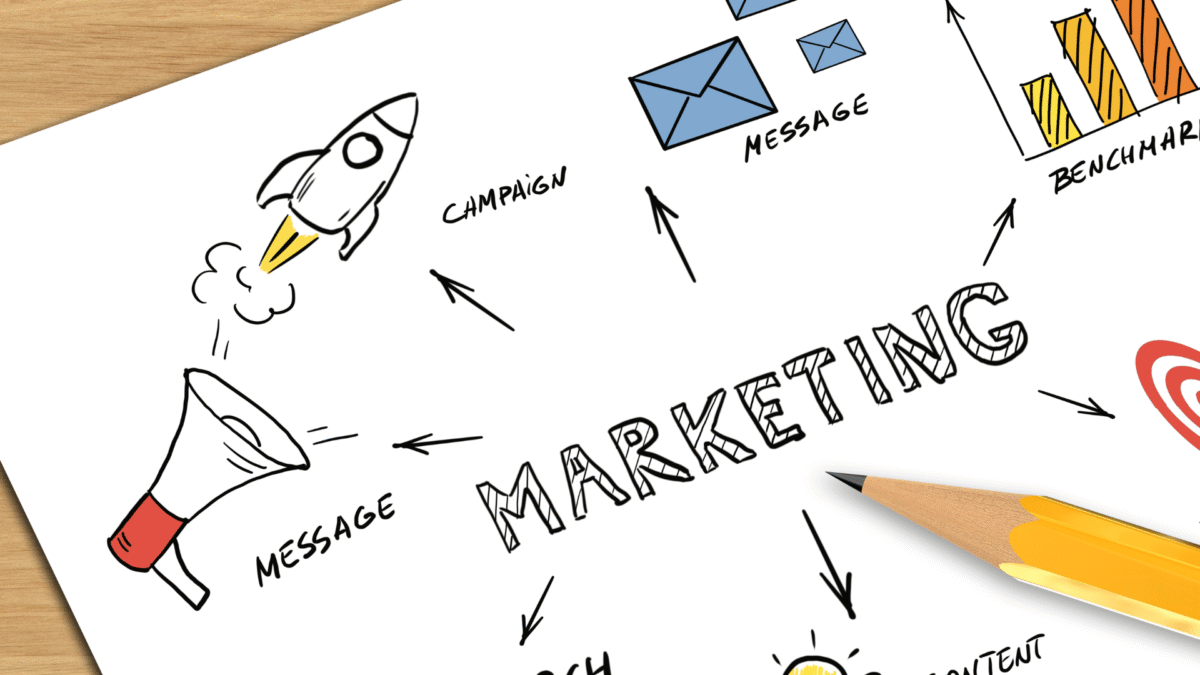企業の集客やブランディングにおいて、SNSは今や欠かせないチャネルになっています。しかし、「WebマーケティングとSNS運用の違いがよく分からない」「どのSNSを使えば効果的なのか」と悩む担当者は少なくありません。数字を追いかけても成果に結びつかなかったり、始め方が分からず運用が続かなくなったりするケースも多く見られます。
この記事では、まずWebマーケティングとSNSの違いを整理し、代表的なSNSの特徴を紹介します。さらに、SNS運用を通じてWebマーケティングを始めるための具体的なステップも解説します。自社に合ったSNSの選び方や運用の進め方を理解すれば、効率的に成果を高めることができます。
WebマーケティングとSNSの違いとは

Webマーケティングは、企業がインターネットを通じて顧客とつながり、売上やブランド価値を高めるための総合的な取り組みです。その中には、検索エンジンを活用するSEOやリスティング広告、メールマーケティング、コンテンツマーケティング、Webサイト改善など、幅広い手法が含まれます。
こうした施策のひとつとして位置づけられるのが、SNS運用です。SNSはユーザーとの距離が近く、リアルタイムでの双方向コミュニケーションが可能な点が大きな特徴です。Webマーケティング全体の中で「認知拡大」「関係性構築」「購買や応募への導線づくり」を担うチャネルとして活用されています。
つまり、Webマーケティングは大きな枠組みであり、SNSはその一部を構成する具体的な手段です。全体戦略の中でSNSをどう位置づけるかを明確にすることで、効果的な運用につなげることができます。
代表的なSNS運用とその特徴
SNSと一口に言っても、それぞれのプラットフォームには特徴や得意分野があります。ターゲット層や発信したい情報の内容によって、適切なSNSを選ぶことが成果を左右します。ここでは代表的なSNSの特徴を整理します。
YouTube
YouTubeは、動画コンテンツを通じて商品やサービスの魅力を深く伝えられるプラットフォームです。短期間で効果を出すのは難しく、撮影・編集といった工数も大きくなりがちですが、その分成果が出れば長期的に活用できる「資産」として残る点が大きな特徴です。
公開した動画は検索や関連動画を通じて長期間視聴され続けるため、他のSNSに比べて継続的な集客効果を期待できます。また、動画はユーザーの理解を促しやすく、購買や問い合わせなど行動につながりやすいことも強みです。
時間やコストを要する一方で、企業の認知拡大からブランド価値向上まで幅広く貢献できるのがYouTubeの魅力です。SNSの中でも資産性の高いチャネルとして、戦略的に取り組む価値があります。
LINE
LINEは、日本国内で圧倒的に利用者数が多く、日常的に使われているコミュニケーションツールです。その特性を活かし、企業が見込み客や既存顧客と継続的に接点を持つチャネルとして有効に機能します。
例えば、クーポン配布やキャンペーン案内を通じて追客に活用できるほか、セミナーやイベントの案内なども高い開封率で届けられます。また、チャット機能を使って顧客の質問に対応したり、自動応答を導入したりすることで、顧客体験を向上させることも可能です。
購買や来店を促進したい企業にとって、LINEは「最もユーザーと近い距離で接点を維持できるSNS」といえます。見込み客を育成し、リピーターにつなげる施策に適しています。
X
X(旧Twitter)は、テキストを中心とした発信が基本のSNSです。画像や動画の準備が必要なプラットフォームに比べると、文字媒体であるため始めやすく、気軽に情報発信をスタートできる点が大きな特徴です。
拡散力に優れており、投稿が話題になれば短期間で多くのユーザーにリーチできます。また、トレンド機能を活用すれば、時事性のあるテーマや最新ニュースに関連した情報発信で注目を集めやすくなります。
一方で、情報が流れるスピードが非常に速いため、継続的に投稿を重ね、ユーザーとの接点を維持する工夫が求められます。リアルタイムでの情報発信やキャンペーン告知など、スピード感のある運用に向いているSNSです。
Instagramは、写真や動画といったビジュアルを中心に発信できるSNSです。テキストよりも直感的に情報を伝えられるため、商品やサービスの世界観を表現するのに適しています。特にファッション、飲食、美容、ライフスタイルといった分野では効果的に活用されています。
また、フィード投稿やストーリーズ、リールなど複数の発信フォーマットがあり、ユーザーの関心をさまざまな角度から引きつけられます。さらに、Instagramショッピング機能やリンク導線を活用することで、認知から購買まで一連の流れを構築することも可能です。
視覚的なアプローチを活かせるInstagramは、ブランドイメージを強化したい企業や、デザイン性や雰囲気を重視する商材を扱う企業に特におすすめのSNSです。
TikTok
TikTokは、短尺動画を中心に発信できるSNSで、拡散力の高さが大きな特徴です。アルゴリズムによって興味関心の近いユーザーに動画が届きやすく、フォロワー数が少なくても多くの人にリーチできる可能性があります。
ただし、話題化や認知拡大には強い一方で、直接的に購買行動を促す力は他のSNSほど高くありません。TikTokからすぐに商品購入につなげるよりも、「ブランドやサービスを知ってもらう入り口」として活用する方が効果的です。
エンタメ性の高いコンテンツが好まれるため、軽快でわかりやすい情報発信を意識することが成功のポイントになります。拡散力を活かして認知度を上げたい企業には相性の良いSNSです。
SNS運用でWebマーケティングを始める方法

SNS運用は、ただ投稿を続けるだけでは効果が見えにくく、成果につながりません。目的を明確にした上で、戦略的に進めていくことが必要です。ここでは、WebマーケティングをSNSから始める際の基本的なステップを5つ紹介します。
- 目標を決める
- 利用するSNSを決める
- アルゴリズムを理解する
- チャンネルを開設する
- PDCAを回す
この流れを押さえておけば、SNSを単発的な施策で終わらせるのではなく、継続的に成果を積み上げる運用が可能になります。
目標を決める
SNS運用を始める際には、まず「何のために運用するのか」という目標を明確にすることが欠かせません。漠然とフォロワー数や再生回数を増やそうとしても、事業の成果に直結しなければ意味が薄れてしまいます。
目標にはいくつかの方向性があります。例えば、新規顧客を獲得したい場合は「サイトへの流入数や購入率」をKPIとすべきです。採用を強化したい場合は「エントリー数や内定承諾率」、ブランド力を高めたい場合は「指名検索数やSNSでのエンゲージメント数」などが目安になります。
最初に目標を設定しておけば、どのSNSを選ぶべきか、どのようなコンテンツを発信すべきかも判断しやすくなります。成果を出すための第一歩は、目的とKPIを明確に結びつけることです。
KPI設定についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
利用するSNSを決める
目標が定まったら、次は自社に適したSNSを選ぶことが重要です。すべてのプラットフォームに手を広げるのではなく、目的やターゲット層に最も合致するSNSに集中する方が効果的です。
例えば、認知拡大を狙うなら拡散力の高いXやTikTokが有効です。ブランドの世界観を伝えたいならInstagram、顧客との接点を維持したいならLINE、専門性を深く訴求したいならYouTubeが向いています。ターゲットの属性や購買行動と結びつけて考えることで、SNS選びを誤らずに済みます。
どのSNSにも特徴があるため、選定段階で「なぜその媒体を使うのか」を明確にすることが、運用を継続し成果につなげるカギとなります。
アルゴリズムを理解する
SNS運用で成果を出すためには、それぞれのプラットフォームが持つアルゴリズムを理解することが欠かせません。アルゴリズムとは、どの投稿をどのユーザーに表示するかを決定する仕組みであり、この仕組みを意識した発信を行うことでリーチやエンゲージメントを大きく高めることができます。
例えば、Instagramではエンゲージメント率(いいね、コメント、保存、シェア)が高い投稿が優先的に表示されやすく、TikTokでは動画の視聴完了率や視聴維持率が拡散の鍵を握ります。YouTubeではクリック率と総再生時間が重要視され、Xでは投稿の鮮度と拡散力が大きく影響します。
各SNSのアルゴリズムを理解していれば、ただ投稿を重ねるのではなく「ユーザーに届きやすい形式や内容」で発信できます。結果として、同じ労力でも得られる効果に大きな差が生まれます。
チャンネルを開設する
SNS運用を始めるには、まず公式アカウントやチャンネルを開設する必要があります。ただ開設するだけでなく、プロフィールや基本情報を整えることが最初の重要なステップです。
アカウント名やアイコン、ヘッダー画像、プロフィール文は、ユーザーが最初に接触する情報です。ここで「どのような企業なのか」「どのような情報を発信しているのか」が伝わらなければ、フォローやエンゲージメントにはつながりません。例えば、企業サイトや問い合わせ先へのリンクを設置すれば、ユーザーがスムーズに次の行動を取れるようになります。
また、チャンネル開設時にブランドカラーやデザインのトーンを統一しておくと、後の発信でも一貫性を保ちやすくなります。初期設定を整えておけば、アカウントの信頼性が高まり、運用開始後の成果につながりやすくなります。
PDCAを回す
SNS運用は、一度投稿したら終わりではなく、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のサイクルを繰り返すことが成果につながります。このPDCAを意識的に回すことで、運用の精度を高め、継続的に効果を積み上げることが可能になります。
例えば、初期の段階で立てたKPIに対して数値を確認し、クリック率やエンゲージメント率が低ければ投稿内容やタイミングを見直します。反対に成果が出ている施策があれば、その要因を分析し、他の投稿にも展開することで再現性を高められます。
PDCAを回す習慣を定着させると、感覚的な投稿から脱却し、データに基づいた改善が可能になります。その結果、フォロワー数や認知度の向上だけでなく、売上や採用といった具体的な成果へと結びつけることができます。
まとめ
Webマーケティングは大きな枠組みであり、その中でSNS運用は「認知拡大」「顧客との関係構築」「購買や応募の導線づくり」といった役割を担います。YouTube、LINE、X、Instagram、TikTokといった主要SNSはそれぞれ特徴が異なるため、目的やターゲットに合わせて使い分けることが重要です。
SNS運用を始める際は、まず目標を明確にし、自社に合ったプラットフォームを選定することからスタートします。そのうえで、アルゴリズムを理解し、チャンネルを整備し、PDCAサイクルを回すことで継続的な成果を積み上げることができます。
SNSは「投稿して終わり」ではなく、戦略的に運用してこそWebマーケティング全体に貢献します。この記事を参考に、自社に最適なSNS戦略を立て、効果的なマーケティング活動へとつなげてください。