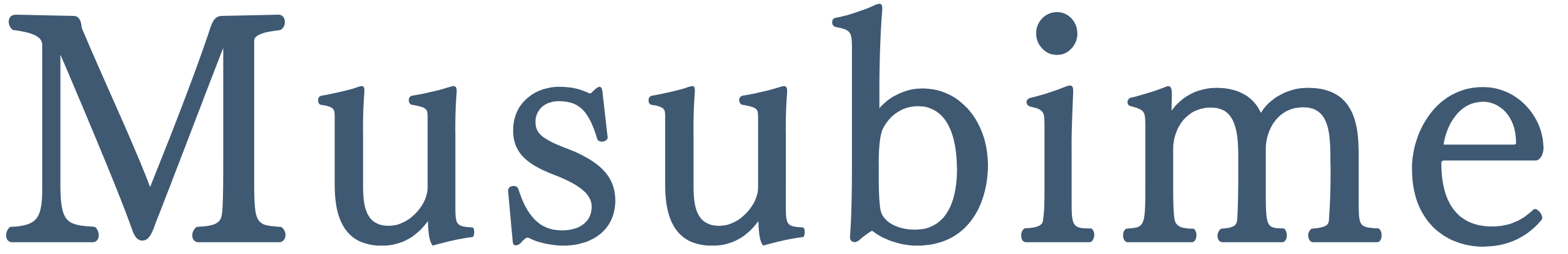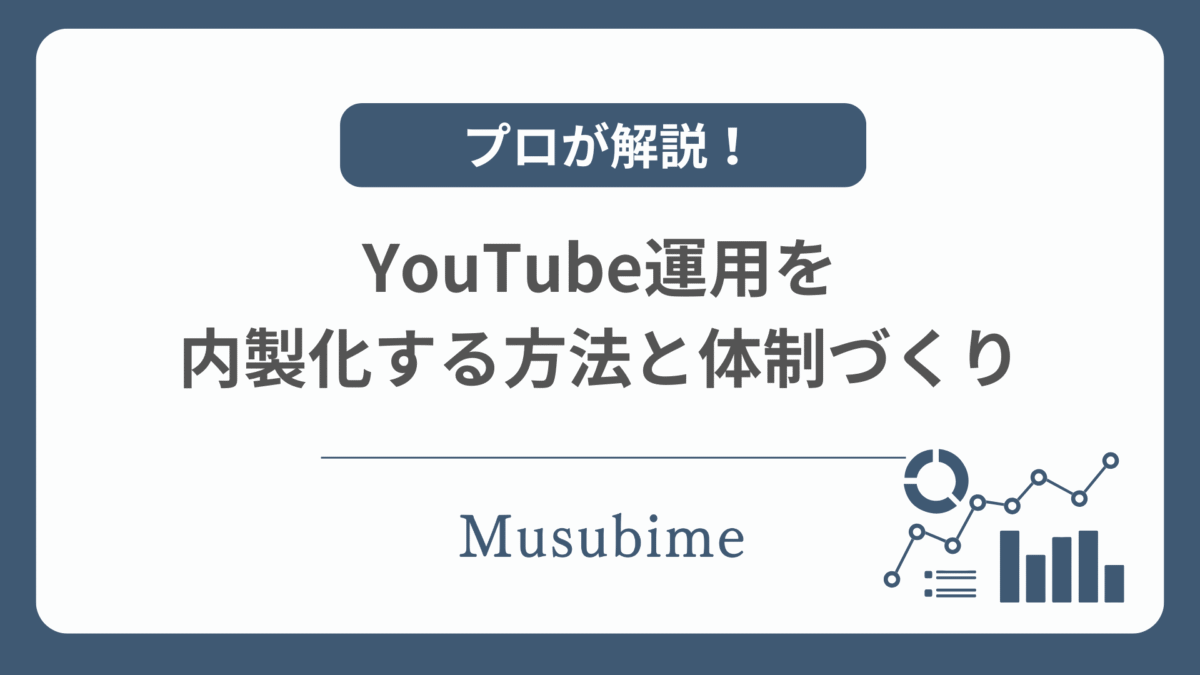YouTubeを内製で運用する流れを上司から求められたものの、何から手を付けるべきか分からず手が止まってしまっている担当者は少なくありません。
人手も予算も限られた中小企業では、動画制作に必要なスキルや機材、人材の確保に課題を感じやすく、方針を明確にするのが難しいのが現実です。
本記事では、企業がYouTube運用を内製化する理由から始まり、実践的な体制づくりのポイントや、スモールスタートに適した戦略まで段階的に整理しています。
YouTube運用を内製化するメリット

YouTube運用を内製化する最大の理由は、コストを抑えつつ、社内にノウハウが蓄積され、他のマーケティング施策との連携もスムーズになるからです。
日々現場を知る社員が関わることで、企業ならではの視点やストーリーを反映させた動画が生まれやすくなります。これは視聴者との信頼関係構築やブランディングにも直結する要素です。
内製化には学習や初期負担も伴いますが、中長期的に見れば自社の資産となる運用体制が築けるのです。
YouTube運用の内製化の3ステップ
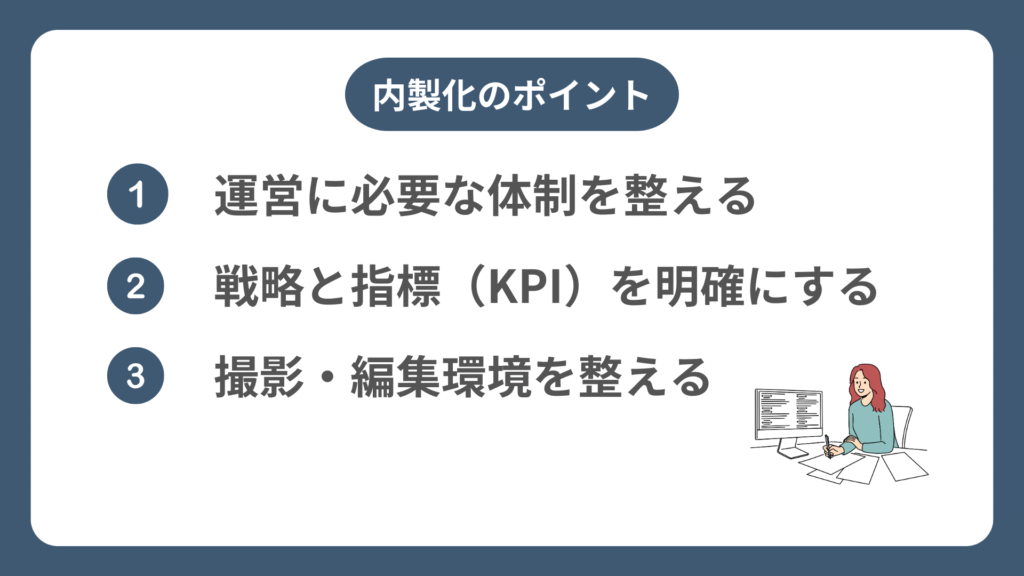
YouTubeを内製でスムーズに運用するためには、段階的な準備が欠かせません。ここでは、体制づくりから戦略設計、環境整備まで、実行に必要な3つのステップをご紹介します。
①YouTube運用に必要な体制と人材を整える
YouTubeの運用を内製化するには、最初に必要な人材を確保することが最優先です。
全てを社内でまかなう場合、7〜10名ほどの役割分担が必要とされます。特に重要なのは、
以下のような主要ポジションです:
| ポジション | 主な役割 | 人数目安 |
| ディレクター | 動画の企画・撮影・編集の進行管理 | 1名 |
| 動画編集者 | 映像の編集など | 2−4名(投稿頻度による) |
| 企画担当 | 構成や台本の作成 | 2名 |
すべてを内製するのが難しい場合は「ハイブリッド体制(企画・ディレクションは内製、編集は外注)」も効果的です。編集や構成作成は外部パートナーに委託しやすく、内製化のハードルを下げる方法として活用できます。
②成果を出すための戦略と指標を明確にする
YouTube運用を社内で行う以上、「何のためにやるのか」「どうなれば成功なのか」を最初に明確化しておく必要があります。
まずはチーム内で、以下のようなビジネス視点のKPIを定めましょう:
- 再生数やチャンネル登録者数
- 自社サイトや採用ページへの導線数
- 売上やリード件数、採用応募数などの成果指標
コンテンツ企画や公開スケジュールもこの目標に合わせて逆算する形で設計します。採用目的が強い場合は「社員インタビュー動画」を定期配信、リード獲得が目的であれば「お役立ち系HowTo動画」や「事例紹介」などが適しています。
その他、コンプライアンスについても、この段階で確認しておきましょう。
チャンネル設計については、以下の記事で解説しています。
③スムーズな運用を実現するための環境を整備する
実際にYouTube運用を社内で行うには、必要な機材や環境を揃えることも見落とせないポイントです。最低限必要な機材は以下の通りです。
- カメラ(スマホでも可、ただし高画質が望ましい)
- 三脚
- 照明
- マイク
- 編集用パソコン
- 動画編集ソフト(例:Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve)
- グリーンバック(背景処理が必要な場合)
これらをすべて揃えると、最低でも40万〜50万円程度の初期投資が必要です。高性能機材を選ぶ場合やスタジオ環境を作る場合は、100万円近くかかることもあります。
社内の不要資産を活用したり、レンタル・中古機材を検討することで予算圧縮も可能です。
YouTube運用の内製化の壁

YouTube運用を内製化しようとすると、想像以上に高い壁が立ちはだかります。特に中小企業や少人数体制では、企画から撮影・編集までのすべてを自社で担うのは現実的に厳しい場合が多いです。
| 動画制作の工数が大きい | 企画・台本作成・撮影・編集・サムネイル作成・アップロード・分析など、工数がとにかく大きい |
| 出演者や環境の整備が難しい | 動画に出たがる社員がいない撮影機材への投資資金が少ない |
| 継続できない | ネタが尽きる、人材の育成やモチベーション管理が難しい |
こうした壁を乗り越えるには、はじめから全てを内製で抱え込まず、一度外注をうまく活用するのが現実的な戦略です。例えば最初の数本を外部の制作会社に依頼し、その過程でフォーマットや運用フローを学んでから内製に移行するというアプローチが有効です。
結果として、いきなり完璧な内製化を目指すよりも、柔軟に外部リソースを取り入れつつ、確実に内製ノウハウを蓄積していくプロセスのほうが成功率は高まります。
まとめ
YouTube運用を内製化することで、自社らしさを活かした継続的な発信が可能になります。しかしその一方で、準備・体制・スキル・継続性など、乗り越えるべき壁が多いのも事実です。
だからこそ、「まずは一部を外注し、流れや仕組みを学ぶ」というステップを挟むことが、結果的にもっとも現実的で効率的な内製化への近道になります。
特におすすめなのが、法人向けYouTube支援に特化した「Musubime(むすびめ)」です。企画・撮影・編集といった一連の運用支援はもちろん、自社で運用するための導入サポートや内製化支援にも力を入れており、少人数体制の企業でも安心して始められます。
まずは、気軽にお問い合わせください。